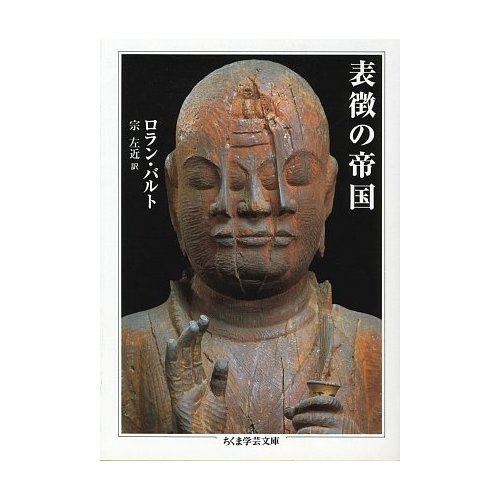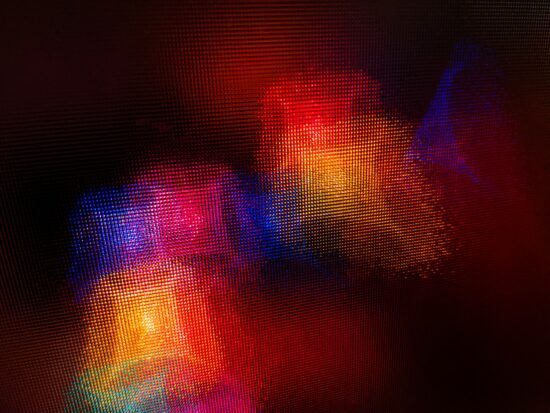ロラン・バルトの「表徴の帝国」に、箸についての興味深い記述があります。
下記に一部抜粋します。
—–
箸は、食べものを皿から口へと運ぶ以外に、おびただしい機能をもっていて(単に口へ運ぶだけなら、箸はいちばん不適合である。そのためなら、指とフォークが機能的である)、そのおびただしさこそが、箸本来の機能なのである。箸は、まずはじめにーーーその形そのものが明らかに語っているところなのだがーーー指示するという機能を持っている。箸は、食べ物を指し、その断片を示し、人差し指と同じ選択の動作をおこなう。食事という日常性のなかに、秩序ではなく、いわば気まぐれと怠惰をもちこむのである。
二本の箸のもう一つの機能、それは食べ物の断片をつまむことである。(もはや西洋のフォークのおこなうような、しっかりと掴まえる動作ではない。)それというのも、食べ物を持ち上げたり、運んだりするのにちょうど必要以上の圧迫が、箸によってあたえられることはないからである。
思うに箸というものは(三番目の機能として)分離するにあたって、西洋の食卓でのように切断してとりおさえるかわりに、二つに分け、ひきはなし、取り上げるものなのである。箸は、食べ物を暴行しない。箸は(野菜の場合)食べ物を少しずつほぐす、または、(魚、うなぎの場合)食べ物をくずす(この点で、箸はナイフよりもはるかに自然のままの指に近い)。
最後に四番目の機能として、そしておそらくこれが箸のもついちばん美しい機能であろうが、二本の箸は、食べ物を『運ぶ』。あるときは、二本の手のようにくみあわされて、ピンセットとしてではなく、支えとして、ご飯の断片のそこにすべりこみ、断片を支えて食べる人の唇のところまで持ち上げる。
箸は西洋のナイフ(そして、猟師の武器そのものであるフォークに)対立する。箸は切断し、ぐいと掴まえて手足をバラバラにして突きさすという動作を拒否する食器具である。箸という存在があるために、食べ物は人々が暴行を加える餌食(たとえば、人々のむさぼりつく肉)ではなくなって、見事な調和をもって変換された物質となる。箸は食べ物を、あらかじめ食べやすく按配された小鳥の餌とし、ご飯を牛乳の波とする。箸は母性そのもものように倦むことなく、小鳥のくちばしの動作へと人をみちびく、わたしたち西洋人の食事の習慣には相もかわらず、槍と刀で武装した狩猟の動作しかないのだが・・・。
—–
ロラン・バルトは、箸は指の延長のようなとても繊細な道具であり、様々な機能をもたらしていると語っています。
ナイフとフォークの文化とは、同じ食の道具としても一線を画します。
初めて読んだときは、あらためて独自の文化を再認識させられた大変興味深い一文でした。
このようなことに出会うたびに新鮮な感覚、感性の扉が開かれるように感じます。